神谷美恵子(1914~1979年)は,ハンセン病に関する精神医学的研究,『生きがいについて』『人間を見つめて』をはじめとした多数の著作で知られる著名な精神科医である.また,フランス語,英語,ドイツ語,イタリア語,ギリシャ語,古典ギリシャ語など多数の言語を操る語学力があり,第二次世界大戦後に文部大臣となった父・前田多門を助け,多門が辞職した後も,GHQの通訳・翻訳などに活躍した.結婚,出産後は,妻・母としての務めを果たしながら,語学教師,大学教員として働き家計を助けた.哲学書,医学書,詩の翻訳も手がけた.以上のように,多彩かつ稀有な才能と能力に恵まれ,偉大な仕事を成し遂げた美恵子だが,その人生は平坦で直線的なものでは決してなかった.「日記」や親友の浦口真左との手紙のやりとりからは,喜びや感謝の気持ちをもちながらも,苦悩や葛藤に満ちた日々を送っていたことが窺われる.美恵子には特有の使命感があり,「デーモン」と呼んだ衝動ともいえるような強い欲求をもっていた.家庭をもつ女性として仕事に向かうことへの強い葛藤も存在した.ハンセン病患者のために働きたいと熱望しながら,美恵子が精神科医として長島愛生園に勤務した期間はそれほど長くはない.本稿では,神谷美恵子が歩んだ人生について,『若き日の日記』と『神谷美恵子日記』,浦口真左との『往復書簡集』に残された美恵子の生々しい言葉や想いに寄り添いながら,求道者として,そして一人の女性としての苦悩を中心に解説した.最後に,美恵子の人生を支えた存在について考察を加えた.
https://doi.org/10.57369/pnj.23-002
はじめに
神谷美恵子(1914~1979年)*1は,ハンセン病に関する精神医学的研究,『生きがいについて』『人間を見つめて』『遍歴』『こころの旅』などの多数の著作で著名な精神科医である.そればかりではなくフランス語,英語,ドイツ語,イタリア語,ギリシャ語,古典ギリシャ語などの多数の言語を操る語学力があり,第二次世界大戦後に文部大臣となった父親・前田多門を助け,多門が辞職した後も総司令部(General Headquarters:GHQ)の通訳・翻訳などを行い活躍した.戦後,神谷宣郎と結婚し,二児をもうけ,妻,母としての役割もこなし,さらにはマルクス・アウレーリウス,ミシェル・フーコー,グレゴリー・ジルボーグ,ハリール・ジブラーンなどの著作を翻訳した.美恵子が日本の精神医学の発展に寄与し,広く文化に与えた影響は計り知れない.
以上の業績・経歴の概略だけでも,美恵子がいかに稀有な才能・能力に恵まれ,多大な仕事を成し遂げたかが読み取れるだろう.しかし,決して美恵子は易々とこのような仕事をこなしたのではない.美恵子には特有の使命感,衝動ともいえるような強い欲求があり,また家庭をもつ女性として仕事に向かうことへの強い葛藤があった.それは,美恵子が書き残し,没後出版された『若き日の日記』『神谷美恵子日記』『神谷美恵子・浦口真左往復書簡集』から知ることができる.
ここでは,主に日記に綴られた生々しい語りを通して,美恵子の生涯を概説しながら,美恵子が生涯もち続けた苦悩,特に求道者としての苦悩,一人の女性としての苦悩に光をあててみたい.
I.神谷美恵子の生涯
1.生まれてから(0~18歳)
1)出生,家族
美恵子は,父・前田多門,母・房子のもとに第二子長女として1914(大正3)年1月12日,岡山市に出生した.きょうだい構成は,兄,美恵子,妹2人,弟というものであった.美恵子自身は,幼少期については暗い印象が残っているといい,泣き虫でうじうじした子どもだったという12).
2)美恵子が受けた教育
美恵子は,1920(大正9)年(6歳)に下落合小学校に入学,その翌年に聖心女子学院小学部に編入した21).1923(大正12)年(9歳),多門が国際労働機関の日本政府代表としてジュネーヴに赴任することとなり,家族も同伴してスイスに渡った21).美恵子はジャン=ジャック・ルソー教育研究所付属小学校に入学し,11歳よりジュネーヴ国際学校中学部に入学した21).9歳から3年半にわたってフランス語での教育を受けたことは美恵子に大きな影響を与えた.フランス語で考えることが最も自然と感じるようになり,この後の美恵子の学ぶ姿勢や探究心の基礎を作り上げたと思われる.
1926(大正15)年(12歳)に一家は帰国し,美恵子は翌年自由学園に編入するが,9月には成城高等女学校に編入した21).同時にアテネ・フランセへ通いフランス語の勉強も継続し,母方の叔父でキリスト教無教会主義の伝道者である金沢常雄の集会で聖書を学んだ.1932(昭和7)年(18歳),兄の勧めもあり津田英学塾本科に入学した.2年生のとき,卒業を前にした美恵子は,塾長から将来何をもって社会のためにつくすのかと問われて戸惑い,どういう道があるのだろうと思ったという7).
2.らいとの出会い(19歳)
1933(昭和8)年(19歳),叔父・常雄にオルガン演奏を依頼され,美恵子はらい療養所多磨全生園を訪れた.「らいという病気について何も知らなかった者にとって,患者さんたちの姿は大きなショックであった.自分と同じ世に生を享けてこのような病におそわれなくてはならない人びとがあるとは.(中略)私の存在そのものがゆさぶられたようであった」7).そして,母性的な看護婦と患者との関係をみて,「私もこの方のように,こういう患者さんのところで働きたい! ここにこそ私の仕事があったのだ!」と強く思い,医師として働くことを希望するが,両親の大反対を受け断念せざるをえなかった9).
3.結核罹患と療養,医学へ(20~25歳)
1)結核罹患と療養
1935(昭和10)年(21歳),美恵子は津田英学塾本科を卒業し,同大学部に進学したが,肺結核に罹患していることが判明する.一度目の療養生活で小康状態となるが再発したとき,美恵子は信州にある両親の別荘に一人で行くことを懇願する9).「世界の名著を原著で読む」と決めた美恵子は,医師の指示通りに規則正しい生活をしながら,読書に没頭し,ギリシャ語で新約聖書,古典ギリシャ語でホメーロス,プラトン,そしてマルクス・アウレーリウスの『自省録』を読みこなしていった9).
2)マルクス・アウレーリウスの『自省録』との出会い
結核に罹患したことによって「役立たずの存在になってしまった」と思っていた美恵子の「生きがいの基礎の発見」を助けたのは『自省録』であった13).美恵子はアウレーリウスが,宇宙的にものを考えること,ものごとを達観することを教えてくれたと述べている13).
3)「変革体験」と「光の体験」
正確な時期は不明だが,この療養中,後に美恵子が「変革体験」「光の体験」と呼んだ現象を経験している.「或る日本女性の手記」として,「発狂か自殺か,この二つしか私の行きつく道はないと思いつづけていたときでした.突然,ひとりうなだれている私の視野を,ななめ右上からさっといなずまのようなまぶしい光が横切りました.と同時に私の心は,根底から烈しいよろこびにつきあげられ,自分でもふしぎな凱歌のことばをくちばしっているのでした」6)と紹介しているが,美恵子の体験ではないかと思われる.
4)結核の治癒,渡米
1937(昭和12)年(23歳)に受けた人工気胸術にて幸い結核は治癒したが,主治医より5年間は結婚しないようにとの指示を受けた9).同年,日本婦人米国奨学金が美恵子に授与され米国への留学が決まった9).翌年に父が在ニューヨーク日本文化会館館長に就任したため,一家で渡米し,24歳の美恵子はコロンビア大学大学院ギリシア文学科へ入学した10).
米国では,25歳の2~6月という短い期間ではあったが,母の勧めでペンドル・ヒルというキリスト教クエーカー派の学寮で過ごした10).多くの人との出会いがあったが,とりわけ一生の友人となる浦口真左との出会いは重要なものであった10).
5)医学へ
この頃,美恵子は父や妹とニューヨークで開催されたワールドフェアを見学に行く.ここから美恵子の日記を引用していく.「朝からWorld Fair見学.(中略)中でも私が一番惹かれたのはPublic Health Medicineと英国の社会事業の部だ.そうした所の前に来ると,私は吸いついたようになって仲々動かないという.その様子を帰って父上ととし子とが代る代る母上に説明した時だった.父上がふと笑いながら言われるには『美恵子は医者になるかな―君も医学にとりつかれたのだろう.それが何か運命なんだろう.いい俺もあきらめた.俺の生きている限り応援してやるからやれ』私はどきんとした.『え? 本気で言ってらっしゃるの?』『うん,そうだよ』父上のお顔はまじめだ」5)(1939年5月13日,25歳)
19歳で医師として働くことを切望してから父の許しを得るまで,実に6年もの歳月が流れていた.
4.医学教育から卒業まで(25~30歳)
1)医学を学ぶなかで
1939(昭和14)年9月(25歳)より美恵子はコロンビア大学医学進学課程で医学を学び始める10).父以外の家族はすでに帰国していたが,時局の悪化,日本が戦争を始めると予測されたこと,日本で医師免許証をとらねば日本で医師として働くことはできないと言われたことより,美恵子も1940(昭和15)年7月(26歳)に帰国した10).1941(昭和16)年(27歳),美恵子は東京女子医学専門学校の本科に編入学する.熱心に勉強をしながら,らいのことは心の底流にあり,卒業を前にした1943(昭和18)年8月(29歳)に長島愛生園に12日間滞在し,光田健輔園長のもとで実習を行っている11).
2)精神医学の世界へ
愛生園行きについての父の反対が絶対的であったこと,東京帝国大学精神科医局長の島崎敏樹と出会い,精神医学に強く惹かれたことから,美恵子は卒業後の進路を精神医学に決めた16).東京都立松沢病院を見学したときに「ここに働く人たちの労苦は癩院に働く人々のそれに優るとも劣らないと思った.(中略)感謝されることもなし人に感心されることも少ない道,この点に惹かれる」3)(1943年12月14日,29歳)と書いている.一方,「レプラに対して悪くて精神科行の決心を決めかねると言ったら(真左から)『あなたはまるでレプラと婚約した人みたい』と笑われた」3)(1944年1月5日)と,気持ちは揺れ動いていた.
3)卒業を前に
卒業を控えた日,美恵子は嗚咽しそうになりながら歩いていた.「『自分からこわれる,自分からこわれる』そうつぶやきながら今にもおえつしそうになる唇をかみしめて私は昨日新宿の通りを歩いていた.『こわれる』とは理想のことを言っているのだった.医師となって人につくすという理想を日々具体化する夢も,現実となって見ると,やっぱりはかないものだった.まず第一にその夢をこわすのがこの自分だ.心身ともに弱すぎる自分,醜い自分―この自分から何のよきものが出よう」5)(同年7月11日).戦局の悪化により,半年繰上げの同年9月に美恵子は東京女子医専を首席で卒業し,医師免許証を取得した3).
5.精神科医として(30歳~)
1)東京帝国大学医学部精神科へ
1944(昭和19)年10月10日(30歳)に美恵子は東京帝国大学医学部精神科医局へ入局し,内村祐之教授のもとで精神科医としての修行を開始する.「この精神科ほど一分の隙もなく身にピッタリと来る仕事があろうとは思わなかった.これをするために生まれて来た,という感じがしてならない」3)(同年10月18日)と思う日もあれば,「自分のいい加減な,派手な性格が学問する態度にまで反映して来るのをこの二,三日痛いほど経験して,まったく不安になってしまった.私に学問する資格はないのではないか.また医師たる資格がないのではないか―と苦しい気持ちで反省する」3)(同年11月19日)日もあった.
また,精神医学の学びのなかで,美恵子は自身の病的な側面に気づいていく.自分の抑うつや躁状態などを列挙し,「要するにSchizothymic[分裂気質]+Zyklothymic[躁うつ的性格]なのだから大部分のPsychopathologie[精神病理学]はverstehen[理解]できる筈だ」3)(1945年1月31日,31歳)と書き,ビルンバウムの「精神病理学」に惹かれるのは「自分のPathologisch[病的]なところをますますはっきりさせてくれるからだろう」3)(同年3月26日)と振り返る.また,美恵子は絶えずchaos[混沌]の淵に生きていると感じ,chaosの脅威を意識し,「あらゆる方向に自分というものが引き裂かれ,ちりぢりになって行くようなあの破滅の感じ」に襲われていた3).そして,精神病にならないために「このchaosから何ものか人に通用するものを形づくること」3)(同年5月15日)を意識していた.
2)戦局の悪化のなかで
1945(昭和20)年3月(31歳),戦局は悪化し,罹災被害者が精神科にもまわされ,瀕死の病人への対応を余儀なくされる.そのなかで美恵子は,「一人の受け持ち医にまかせきりで,こういう人たちに目もくれない医者が多いのに驚く.『自分は医者らしいことは嫌いだから.もうそんな内科や外科のことは忘れてしまったから』―これが言訳になろうか.医者になることは即ち,苦悩に悩む人と切っても切れぬ縁を結ぶことではなかったのか」3)と憤慨しつつも,「医者であってしかも人の苦悩に無関心であってもよいということは私には考え難いことだった.医者になる動機は何を措いてもまず人への奉仕であるべきだと私は理屈なしに思い込んでいた.ところが何もそう決まったことではなかったのだ.(中略)私は何というオバカのオボコなんだろう」という思いに至る3)(同年3月19日).
その後,空襲で東中野の家が焼かれるが,美恵子には「宮城,大宮御所までやられた由,私共がやられたのも当然であり,むしろ人並になって良かったという気さえ起こ」5)(同年5月26日)ったという.家族は疎開したが,美恵子は東大精神科病棟に住み込み,診療と勉強に取り組んだ11).
6.終戦後,父を助けて
1)終戦,父への思い
同年8月の終戦直後,父・多門が文部大臣に就任する.美恵子は「父の仕事は考えれば考えるほど責任が重く,果たして父が少しでもそれを果たすことが出来るだろうかと,私自身重荷にうちひしがれるような感じを持つなんて僭越で滑稽な話かも知れませんが,父と私との昔からの密接な関係をお考えになれば自然とおうなずき下さるでしょう.新潟県知事の時と同様,今度も父の就任が決まった直後,最初に父に逢った家族は私一人でした.帝国ホテルにかけつけた時,父は一言『大変なことになった』と申しました.その時私は『いいじゃない,この事のために死んだって』と申しました.そして,私自身,全力をあげて父を助けよう,と心に誓いました」4)(同年9月2~26日)と真左へ打ち明けている.
2)美恵子の葛藤
医局の仕事を休み,文部省での書類の翻訳などの仕事を開始するが,美恵子は葛藤する.「自分のほんとの生地だけ出して生きたくてたまらなくなる.ほんとの生地とは『出たら目』だ.私は自分の裡なるaesthetisch[審美的]なもの,religiös[宗教的]なもの,wissenschaftlich[科学的]なもの,sozial[社会的]なものをどういう風に統合したらいいのかよく分からない.どうもその一つ一つに違った方向に惹かれ,うっかりすると八つ裂きになりそうだ.それらすべてが各々性欲とか食欲とかいう本能と同じ力で―否,これらも本能そのものなのだろう.そう思うからこそニーチェに共鳴する.(中略)全く七つの悪鬼に取り付かれたとはこの私のことだろう」3)(同年10月18日)美恵子は,これらの本能,衝動を鬼,デーモンと呼んだ3).
翌1946(昭和21)年(32歳),父が辞職した.その後任の安倍能成大臣に請われ,美恵子は引き続きGHQなどの通訳・翻訳の仕事を続ける.5月に安倍の辞職と同時に美恵子も辞職し,東大精神科医局の仕事に戻った.
7.神谷宣郎との結婚,育児(32歳~)
1)宣郎との結婚
東京帝国大学理学部植物科講師の神谷宣郎との結婚が決まり,美恵子は「彼の愛と理解は丁度この春の慈雨のように私の上にふりそそいでいる.(中略)私にこのような春を迎える権利があるのか,とただただ勿体ない気がする.沢山の不幸せな人々を思うとどうしていいかわからないような気がする」3)(1946年2月16日,32歳)と戸惑いながらも,愛を深めていく.同年7月に結婚し,四畳半の一室を借りて住む.医局の仕事は週3回となり,宣郎の学者としての大成を願い,家計を助けるため和文英訳のアルバイトなどに追われる生活となった.
2)育児とアルバイトの生活
翌1947(昭和22)年4月(33歳),長男が誕生した.美恵子は英独仏語の家庭教師のアルバイトを開始した.1949(昭和24)年(35歳),宣郎が大阪大学理学部教授として単身赴任するなか,12月に次男が誕生した.この年に美恵子が翻訳したマルクス・アウレーリウスの『自省録』が出版されている.1950(昭和25)年(36歳),宣郎が渡米し,美恵子は2人の子どもを育てながらアテネ・フランセでフランス語を教え始めた.1951(昭和26)年(37歳)に宣郎が帰国し,美恵子は東大医局を辞して,一家は芦屋に移った.美恵子は神戸女学院大学の非常勤講師となるも,「この頃の鬼の荒れようは物すごく,幾度自棄的な気持になったか知れない」5)(1951年10月16日)と苦しむ日々が続いた.
3)大阪大学医学部神経科へ
同年11月に美恵子は大阪大学医学部神経科に研究生として入局し精神医学の勉強を再開した.しかし,1953(昭和28)年(39歳),3歳半の次男が粟粒結核に罹患していることが判明し,高価なストレプトマイシンを購入するため,美恵子はフランス語の私塾を始める21).1954(昭和29)年(40歳),神戸女学院大学英文科助教授に就任するも,家計は苦しかった.「毎日英文直しをしているといらいらして自殺をしたくなる.人生とはしたくない事をする場合なのだろうか.いつまで語学の先生をしなくてはならないのか.語学よ,汝は私の呪いだ.このような事にこんなに時間をとられていては,いつまでたっても精神医学者として立つことはできない.(中略)私は毎日をかしこく生きて何とかしてあまりモーロクする以前に目的を達せねばならない.私でなくてはできない精神医学上の仕事を果たさなくてはならない.」5)(同年8月27日)と苦しみながらも自身を鼓舞する.長男が7歳,次男が4歳の頃であった.
8.長島愛生園での研究,『生きがいについて』の執筆へ(43~58歳)
1)子宮がんの発覚,精神医学研究へ
1955(昭和30)年(41歳),母が逝去した.美恵子に初期の子宮がんが発覚したが,ラジウム照射にて食い止めた5).宣郎の勧めで,大阪大学神経科・金子仁郎教授にらいの精神医学的研究を申し出,許可を得た.1956(昭和31)年9月(42歳),13年ぶりに長島愛生園を訪れ,第1回の調査を行う.1957(昭和32)年4月(43歳)より愛生園の非常勤講師となり,診療のかたわら,1958(昭和33)年(44歳)までにのべ50日間をかけて精神医学的調査を行った21).
2)美恵子の悲しみ
長年焦がれ続けてきた愛生園での診療や研究だが,美恵子の気持ちは複雑であった.「島*2行き.いつもこの旅に出る時が近づくとN,R,T*3との別れが悲しくて気が沈んできて困る」8)(1957年10月30日,43歳),「今日が近づくにつれてNと子どもたちをおいて出て行くのがつらくなり,ここ二,三日よく眠れなかった.自分が冷酷な悪人のようにも思えてくる.汽車の中でも二人の男の子を連れた母親の姿に目をうばわれていた」8)(1958年3月28日,44歳)と,自分を責め苦しみや悲しみに苛まれていた.
3)ゴッホからの啓示,『生きがいについて』の執筆へ
月に1度か2度の島通いを続けながら,学位論文「癩に関する精神医学的研究」を執筆していたが,ゴッホ展を観にいった際,美恵子は自分も表現に身をささぐべきこと,余生をその使命にもやしつくすべきであるという啓示を直観する5)(1958年12月20日).宣郎も賛成し,「『イミ感について』という書きものをまとめてみたい.パトロギッシュ[病的]な場合もふくめて」5)(1959年11月10日,45歳)と内容も固まり,学位論文完成後『生きがいについて』の執筆を開始した.
4)長島愛生園での診療
1960(昭和35)年(46歳),大阪大学より医学博士の学位を授与され,神戸女学院大学教授に就任24)後も,美恵子は愛生園での診療を継続した.
「今日もまた出て来られた.校務多忙で疲労気味だし,子どもたちやNのこともいつも不安だ.でも家の者はみな元気で私がこうして時どき『家出』するのも今ではあたりまえのことのようにうけとっているらしい.ただ私の心だけが,いつでもひき裂かれる」8)(1961年6月10日,47歳),「ゆうべも家族との別れがちかづくに従って憂うつになり,くちもきけなくなった.」8)(同年7月24日)と悲しみは続くも,島通いは,美恵子にとってやむにやまれぬ道であった17).
一方,島での診療においても葛藤や苦しみは生じていた.「水ぶろに入り,すぐねてしまう.何だか人の心のごみためになってしまった感じ.(中略)らい療養所のようなところでも,やはり大多数の人間は外部の社会と同じく,末梢的な神経だけをすりへらして暮らしているのだ.欲望,ねたみ,いらだち,憎悪―自己に執し,自己をひたすら防禦しようとする姿勢のくるしさ.その無理,その無駄.しかし,考えてみれば自分だってそうではないか」8)(1960年7月21日,46歳)
患者とのかかわりのなか,「『自分はもう何の楽しみもない.手も足もだめで,すっかりやられてしまった.他人の罪もみんな負わなくてはならない』と沈うつな調子で語っているうちに,突然『しかし,こうして思っていることを聞いてもらうのは心の慰めだ』という柔らかいことばがそれまでの固さを破ったのにはおどろいた.(中略)今度はずいぶん多く考えさせられた.ともかく,よどむことに抵抗するところに生きるよろこびがあるのだ.」8)(同年10月22日)と学ぶこと,気づかされることも多くあった.
真左へこう書き送ることもあった.「ここの患者さんの気むつかしいこと,おそらくあなたに想像できないほどでしょう.ゆうべも私は二,三十分,一人の人から罵倒されつづけました.しかも私がした事でもない事について.それでも黙って笑ってすます,という事にだんだん馴れました.そのあと当直室でぐうぐうねてしまった位ですから,こちらの神経も大分太くなったのでしょう.人間というものは,どこまで攻撃的になりうるものか,ここへ来てからつぶさに知ったようです.結局らいという大きな不幸を背負ったくるしみのはけ口としてどこかへ怒りをぶちまけたいのでしょうね」4)(1967年4月29日,53歳).なお,1962(昭和37)年(48歳)に父・多門が胃がんのため逝去した.
5)精神科医として
美恵子は精神医学研究をきっかけとして1957(昭和32)年4月(43歳)に愛生園の非常勤職員となった21).1965(昭和40)年(51歳)には精神科医長となり,月に2度,水曜から土曜の勤務を続けた(図).1967(昭和42)年(53歳)には医長から非常勤となり,1972(昭和47)年4月(58歳)には健康上の理由で愛生園を辞任している8).この15年間,精神科医として,美恵子は何を思い,どのような診療をしていたのだろうか.日記には,島の「ひとりひとりの患者のことを考えると,ほんとうにたまらなくなる.人力以上のしごとなのだろう.私にはできないことなのだ.ただその方向を向くだけしかできない」8)(1961年5月14日,47歳)とある.
加賀乙彦の『フランドルの冬』の書評に美恵子は「精神科医とは,自分をまったく鈍感にしてしまわないかぎり,人間存在の根底によこたわる深淵のようなものに,たえず直面していなければならない因果な職業である.人間の能力を越えた面,人間には資格のない側面を持った職業である.そのためか,本気で仕事にとりくめばとりくむほど,この仕事からも時々脱出したくなるものだ」15)と書いている.同僚の髙橋幸彦からみた美恵子は「患者さんを診察していても,この人の考えのなかで,苦しみのなかで,どういう方法がこの人にとっていちばんいいのか,ということを共に考えてあげる.その人の精神の自由性というか,そういうふうなことを尊重」していたという25).
9.晩年の日々(58~65歳)
1971(昭和46)年12月(57歳)に最初の狭心症発作を起こし,その後は,狭心症,一過性脳虚血発作などで入退院を繰り返した21).しかし,幸い大きな後遺症を残すことはなく,小康状態のときは家事,読書,原稿書きに打ち込んだ20).晩年の思いを抜粋する.「沢山の病める人の,ただひとりをもいやせぬ無力さも,神にゆだねまつりて残る日々をひたすら生きぬかんのみ.医師になってみても何一つ人間のことをわかっていないのを知る.これを知るための勉強であったらしい」5)(1972年10月18日,58歳),「私は痴呆や半身不随の近くにまで行って,ようやくすべてのものから自由になった気がしている.何よりも自分の限界をいやというほど知った,というイミで」5)(1974年12月31日,60歳),「残された日々を大切に生きたい.しかし頭痛や足痛があるときは全存在が痛みそのものになるのをどうしよう」5)(1978年6月17日,64歳)など,自身を神にゆだね,これまでのことを振り返り,体調と折り合いをつけながらの生活だったと思われる.
次男の妻は,晩年の恵美子がたくさんの話をしてくれたこと,ヴァージニア・ウルフや精神医学関係の資料を読んでいて,「あー面白い」「ふしぎだなあ」と感嘆を漏らしていたこと,その声はミミと呼ばれていたという少女時代を想像させるほど若々しく,生き生きとしていたことを報告している19).宣郎によれば死期の近づいた頃には毎日のように,残るものに対して感謝と祈りの気持ちを漏らしていたという20).1979(昭和54)年,一過性脳虚血発作で3回の入院を繰り返したが,10月22日,一時帰宅中に急性心不全の発作を起こし,岡崎市立病院にて死去した.65歳であった21).
II.美恵子の苦悩について
1.求道者として
自分の内面のことや本質的なことを考え,文学や芸術に惹かれていた美恵子は,津田英学塾時代に,何をもって社会のためにつくすのかと教師に問われて困惑する.しかし,その直後に多磨全生園にてらいに出会い,医師としてらい者のそばに立つことを切望するようになった.その後結核に罹患したが治癒したことも,「なぜ自分だけが」という申し訳なさにつながり,より一層,病む人のそばにいることを希求するようになったと思われる.美恵子は「今はもはや自分のために苦しんでいる時でも喜んでいる時でもない」5)(1939年4月2日,25歳),「もし私の使命と信ずる処を単なる便宜などのためにすてたら自分自身に対するrespectを失うだろう」5)(同年12月18日)と自分の使命や歩むべき道を確信する.しかしその一方で,思いが揺れ,「私はナイチンゲールやジャンヌ・ダルクではない.できることならこの使命感から解き放たれて,平凡な静かな,女としての生涯を送りたい」5)(1943年8月27日,29歳)と思うこともあった.
美恵子の「この使命感」とは,1つには「専ら人を愛する道として医学にたずさわ」(1944年4月29日,30歳)るというものであり,美恵子の主観的な「私に感じられる神,私の全身にピリピリ伝わってくる霊感のようなものに従って」生きるということであり,本能的なものであった3)(同年11月26日).
さらに,美恵子はさまざまなことに強く惹かれ,「自然科学的な客観性と探究欲 芸術的な観照と官能 道徳的な潔癖と抑制 宗教的な没入と諦観 これをみんなかかえてどうやって生きて行くか―が依然私の問題だ.はち切れそうな,千々に炸裂しそうな頭を抱えて」3)(同年11月28日)いた.
また,病む人のそばに立つだけではなく,それを何らかの形で表現したいという強い欲求ももっており,「人目の届かぬ病床の傍で患者―即ち『人間というもの』『人生というもの』―と人間的に学問的に『一騎討ち』を為し,じいっと眼を凝らし,耳をすませて自他を観察し,『本質的なもの』をがつがつと喰うて消化し,己が血となし肉となし,その血と肉を注いでものを書く生活.社会のうわつらに賑やかに派手に浮んで,いい加減な言葉や行動を弄ぶ生活と正反対の『現場』の生活.地味で,真剣で,しかも詩味あり,涙あり,ユーモアある生活.社会を国家をどうしようなどと大言壮語を吐くのではなく,つつましやかに人生の悲劇と詩と,美とを味わう生活」3)(1945年10月25日)に憧れを募らせた.
仕事欲も強く,戦後GHQの翻訳をしながら,「一つ一つの刺激に対して仕事欲がむらむらとおこって来る.そうして結婚生活に対する不安をよびさます.いくら頭で覚悟してもいざとなったらこの『仕事の鬼』が家庭生活を破かいしてしまわぬと誰が保証出来よう.書きたい!研究したい!研究発表したい……というこの燃えるような衝動はどうしたらいいのか」5)(1946年1月30日,32歳)と惑う.
以上のように求道者としての美恵子の苦悩は,苦しむ人のそばに医師として立つということ,自然科学・芸術・道徳・宗教への強い欲求,仕事欲,研究欲,表現への憧れといったさまざまな衝動に引き裂かれそうになるという内的な問題が1つである.そして,もう1つは外的・現実的な問題であり,特に結婚後,自身の道を歩むことが困難である期間が長く続いたことであった.家庭をもち,精神医学から離れている時期は「本心は心の本拠は,あくまで病める人,苦悩する人々と共にあるのだ.その世界での仕事をなしとげるまで私の使命は終わらないのだ」2)(1959年9月24日,45歳),「私はもう46歳,そしてガンのためにうけたラジウムの影響からまだ完全に立ち直っていない.(中略)残る寿命と力とで,私はどうしても自分の使命を果たさなくてはならないのだ.果たさない中は死ぬことも許されないのだ.誰がこのintense[激しい]な使命感を理解してくれよう.(中略)私の中には私の理解を超えるものがある」2)(1960年5月15日,46歳)と自身を鼓舞し続けた.
愛生園に通うことができるようになってからも,家族を残していくことの苦悩,患者の苦しみに寄り添うなかでの精神科医としての苦労や苦悩は上述した通りである.
しかし,長きにわたるこれらの苦悩や葛藤を抱え続けたからこそ,特に『生きがいについて』という著作において,美恵子が抱えた多くの衝動や経験を豊かに包含したものをまとめ上げることができたのではないかと思われる.他の著作も同様であり,仮に美恵子がこれらの苦悩をもたなかった場合には,まったく別のものとなり,長く読み継がれることはなかったのではないかとさえ著者には思われる.
2.一人の女性として
美恵子は,自分が「女であって同時に『怪物』に生まれついた」5)(1944年3月2日,30歳)と思い,「女に生まれてこんな性格を持ったとは何という悲劇であろう.その上こういう運命を負わされたとは」5)(同年12月17日),「女なるが故に自己の仕事に没頭する道を行くことはグロテスクなものになりやすい.何と言う冒険を敢えて犯そうとしているのだろう,と時折愕然と気付く」5)(1945年2月17日,31歳),「私は残念ながら実に男じみた頭脳の持主だと言わねばならない.境遇の上でも素質の上でも,私は正常の人生から締め出されているのをつくづく感じる」5)(同年12月9日)と,通常の女性とは異なることを強く自覚していた.
また,女性のもつ「母性というものは,その生物学的な姿においては眼前の子供にまったく吸いつけられるもの」であり,高度の精神生活とは無縁であり,「故に女性で精神的創造をやろうという場合には,母性であることを断念する」ほうがよいのかもしれない,と述べ,創造的な女性に深刻な分裂があることを指摘している2).
それにもかかわらず,娘,妹,姉,妻,そして母,と一人の女性としてのさまざまな役割を美恵子はこなし,創造的な仕事を成し遂げた.娘として戦後,文部大臣の父・多門を強力に支え,結婚後は,学者としての宣郎の大成を願い支えながら,早産だった長男や大病を得た次男の養育に全力を尽くした.宣郎への愛と尊敬,母親としての幸福感もあり,家庭生活は充実していたものと思われる.日常生活の家事,育児,生活を支えるための仕事に忙殺され,自分の道や目標が見失われ,諦める女性は少なくないものと思われる.しかし,美恵子は,決して諦めず,苦しみながらも自分の道を歩むこと,そして家庭人としても生きることを選んだ.島へ行くときの罪悪感,口がきけなくなるほどの沈うつは,長く島へ通うなかでも続き,一人の女性として,妻として,母としての苦しみや悲しみももち続けていたように思われる.
また,美恵子は女性の精神的独立や創造を阻むものは女性自身の内部にあること,それを認識することの必要性についても述べ,女性の創造の困難性について考え抜いていた2).これによって美恵子は『生きがいについて』をはじめとした創造的な仕事・表現に身を注ぐことができたのではないかと思われる.
3.美恵子を支えた存在
精神科医として仕事をするなかで,美恵子は自身の精神病理に気づいていった.発症の恐怖については定かではないが,中井久夫は,「神谷美恵子が精神病の恐怖を秘めていたとしても当然であり,実際,多くの精神病患者が挫折したところで辛くも成功したということさえできる」24)と指摘している.この指摘を読んだとき,著者は美恵子の激しい表現への欲動を思いながら,フランスの女流彫刻家のカミーユ・クローデル,そして日本の彫刻家・詩人である高村光太郎の妻・智恵子のことが頭に浮かんだ.2人とも創造の世界で生きようともがき,パートナーとの関係性やそこでの負荷と深く関連し精神病を発症したことが推察されている22)23).美恵子も強い衝動や葛藤の多い人生を送っており,そこで成功したことは,中井によれば「両側が断崖である痩せ尾根を走りとおすこと」24)であった.
仮に美恵子が精神病の恐怖を抱えていたとして,その発症を免れることができた要因,防御因子はあったのだろうか.1つには美恵子自身の自己理解の深さ,多くの苦難への対応能力の高さがあるだろう.また,美恵子の神,息子達をはじめとした家族,プラトン,マルクス・アウレーリウス,ニーチェ,浦口真左,そして,「ほとんど唯一の,この世で出会った師」と仰いだ三谷隆正14)の存在も美恵子を支えたと思われる.
そのなかで美恵子にとって最も重要だったことは,宣郎の存在や理解であったと著者は考える.次男の徹は,美恵子の生誕100年記念の集いにおいて「母はあんまり冗談の通じない人でした.写真で見るといつもにこにこしているみたいですが,結構激しく泣いたり怒ったり,喜怒哀楽の激しい人だったと思います.というのも私の父が非常におだやかな人でしたから,よけいにそう感じたのかもしれません」1)と語っている.宣郎の安定したおだやかな人格や態度,また美恵子を深く理解し,その道を達成することを応援し援助したこと,それが美恵子を守り支えたことが推察される.
真左に書き送った手紙に印象深いものがある.「この間論文まとめに熱中している時,私のへやに主人や子供たちがちょくちょく入って来ても,『えっ?』と言ってふりむくだけで,さて何を言ったらいいのやら,まったくべつの国の人に出会ったような工合にとまどって,何一つ言葉も出て来ない有様,ほんとうに家族には気の毒でした.((極秘)ちょっと他人に言えないことですが……ふしぎな事に主人はそういう私を『神々しい』(!?)と言い,子供たちも論文がうまく捗っているか大へん心配してくれます.これはじつに勿体ない有難いことで,せめて私が正気になって現実の世界に戻っているときだけでも,皆に恩返しや罪ほろぼしをしたいという気持で私を一杯にします.)」4)(1965年4月7日,51歳).宣郎が美恵子を“神々しい”と思うまでの敬意を払っていたことを示すエピソードと思われる.
また,美恵子は「Nは昨日上京した.2人は仲がいいのに―あるいは仲がいいからかえってそうなのか―彼と離れると私は時間的にはもちろん精神的にもほんとうにゆっくりとなる」2)と書いており,密着しすぎない夫婦関係も美恵子を安定させたものと思われる.
美恵子の逝去後,宣郎は「島に行く日が近づくと,彼女はいつも悲しく憂うつになった.その悲しみの原因は,子供を残し夫を残して行く自分が“冷酷な母親”“悪い妻”に見えたことにあったのであろう.しかし一方では彼女のうちなる“声”―あるいはデーモンといった方がよいかもしれぬ―が彼女に島に行けと命令する.なんという矛盾であろう.両立し難いものを両立させようとする彼女の心は,自分でもよくわかっていたように,矛盾のかたまりでもあったのだ.見方によっては悲劇的であったともいえる.(中略)一たび家を出れば,もはや妻でもなく,母でもない,一求道者としての人間神谷美恵子の姿がそこにあった」20)と書いている.宣郎が美恵子の悲劇や苦悩を肌で感じながら支え,宣郎自身も求道者の夫であり続けるという偉業を成し遂げたように著者には感じられる.
おわりに
神谷美恵子の生涯について美恵子の日記にある思いや語りを中心に述べ,求道者として,一人の女性としての苦悩について考察し,最後に美恵子を支えた存在について述べた.美恵子の多くの業績は才能と努力の賜物ではあるが,多くの困難に直面し,内的な葛藤を抱え続け,病む人苦しむ人のそばに立ち自らも苦悩したからこそ,なお一層の輝きを放っているように著者には思われる.本稿を機に,美恵子の存在や著作が思い出され,再吟味され,現代の精神医学,病める人のために生かされ続けることを心より願う.
編 注:第117回日本精神神経学会学術総会教育講演をもとにした総説論文である.
なお,本論文に関連して開示すべき利益相反はない.
謝 辞 第117回日本精神神経学会学術総会での教育講演と本稿をご理解くださり,貴重な写真の使用をお認めくださった次男 神谷徹様と夫人 永子様に心より御礼申し上げます.
1) 樋野興夫, 石田雅夫, 神谷 徹: 神谷美恵子を語る―医師として, 母として―. 神谷美恵子―「生きがい」は「葛藤」から生まれる― (河出書房新社編集部編, KAWADE夢ムック 文藝別冊). 河出書房新社, 東京, p.199-207, 2014
2) 神谷美恵子: ひとりごと. 人と仕事. みすず書房, 東京, p.85-108, 1983
3) 神谷美恵子: 若き日の日記. みすず書房, 東京, 1984
4) 神谷美恵子, 浦口真左: 往復書簡集. みすず書房. 東京, 1985
5) 神谷美恵子: 神谷美恵子日記. 角川書店, 東京, 2002
6) 神谷美恵子: 心の世界の変革. 生きがいについて. みすず書房, 東京, p.243-268, 2004
7) 神谷美恵子: らいと私. 人間をみつめて. みすず書房, 東京, p.129-149, 2004
8) 神谷美恵子: 島日記から. 同書. p.201-257
9) 神谷美恵子: 帰国. 遍歴. みすず書房, 東京, p.63-99, 2005
10) 神谷美恵子: ペンドル・ヒル学寮の話. 同書. p.101-165
11) 神谷美恵子: 現実の荒波の中で. 同書. p.167-309
12) 神谷美恵子: 「存在」の重み―わが思索 わが風土―. 本, そして人. みすず書房, 東京, p.2-16, 2005
13) 神谷美恵子: 生きがいの基礎. 同書. p.17-24
14) 神谷美恵子: 愛に生きた人. 同書. p.123-124
15) 神谷美恵子: 加賀乙彦『フランドルの冬』書評. 同書. p.224-226
16) 神谷美恵子: 心に残る人びと. ケアへのまなざし. みすず書房, 東京, p.28-39, 2013
17) 神谷美恵子, 外口玉子: 対談・病める人と病まぬ人. 同書. p.96-114
18) 神谷美恵子: うつわの歌, 新版. みすず書房, 東京, 2014
19) 神谷永子: 晩年の日々. 神谷美恵子の世界 (みすず書房編集部編). みすず書房, 東京, p.154-159, 2004
20) 神谷宣郎: 神谷美恵子 人間として妻として. うつわの歌, 新版 (神谷美恵子著). みすず書房, 東京, p.177-183, 2014
21) みすず書房編集部編: 神谷美恵子の世界 みすず書房, 東京, 2004
22) 宮本忠雄: カミーユ・クローデル. 『作品のこころ』を読む. 吉富薬品株式会社, 大阪, p.13-16, 2007
24) 中井久夫: 書評『神谷美恵子』江尻美穂子著. 時のしずく. みすず書房, 東京, p.201-204, 2005
25) 髙橋幸彦: 神谷美恵子先生のこと. こころの旅 (神谷美恵子コレクション) 付録 (3). みすず書房, 東京, 2005


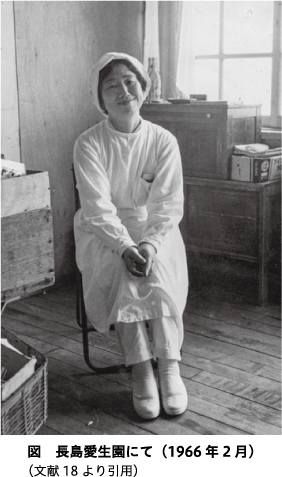




*1 美恵子の語りを中心とするため,「美恵子」という表現,当時の社会的状況から一部「らい」という言葉を用いる.
*2 長島愛生園
*3 宣郎,長男・律,次男・徹のこと