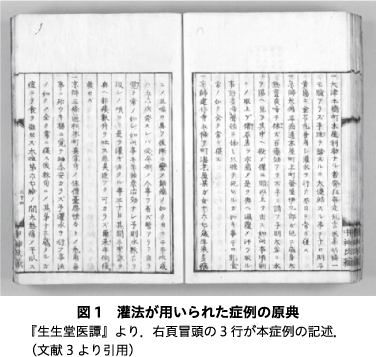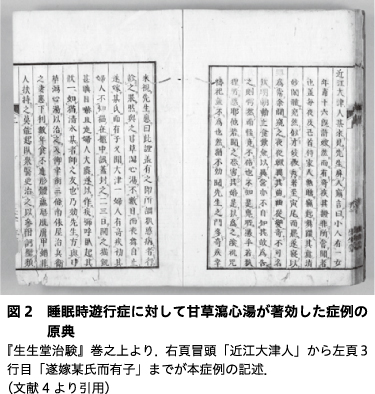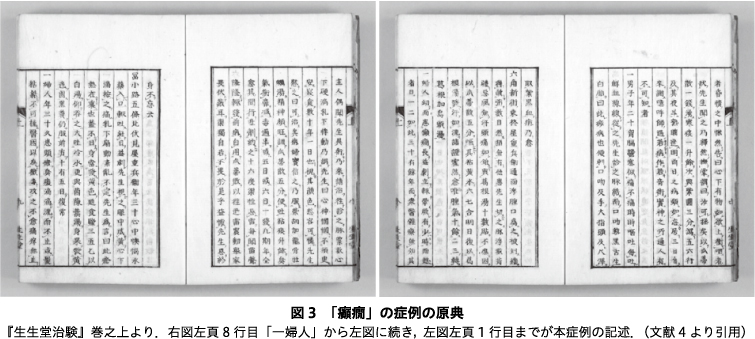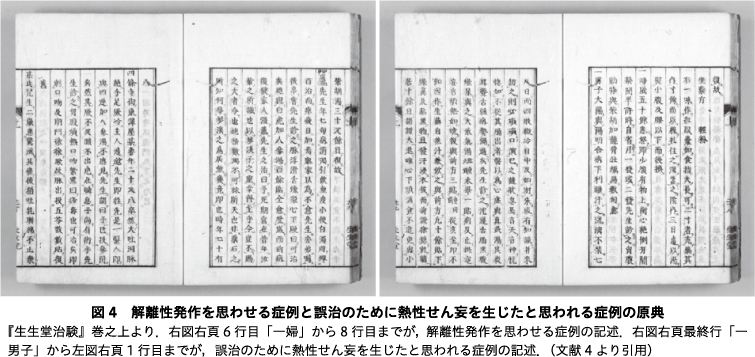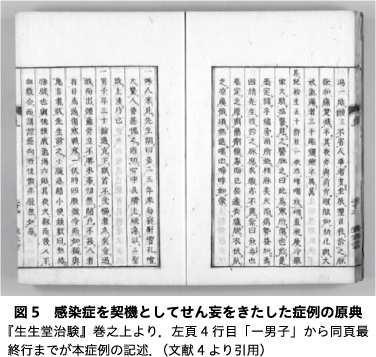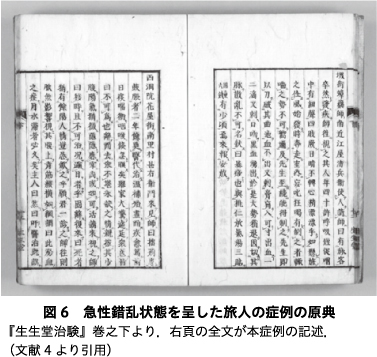漢方医学は,中国の古典に依拠しつつも,室町時代後期から江戸時代を通じて,わが国で独自に育まれてきた,わが国固有の伝統医学である.現代精神医学的視点でとらえる限り,近代までの漢方医学において,精神症状の評価や精神障害に対する治療方法が探求されてきた形跡はほとんどなく,精神療法のあり方にかかわる具体的な言及に至ってはほぼ皆無である.そのようななかにあって,中神琴渓(1744~1835)は,近世から近代の漢方医学史のなかでおそらく唯一,精神障害の治療を積極的に応需し精神症状を詳述した極めて特異な医家であり,その功績は注目に値する.中神琴渓は,卓越した病態観察眼にもとづき,最適な治療戦略を提案し,個別性の高い医療を実践した.他方,臨機応変を是とし,書を著すことを嫌い,固定観念や先入観に惑わされることを厳しく戒めた.しかし,門弟たちが,歴史に埋没することを惜しんで師の医療を後に書として編纂したため,それらの著述により中神琴渓の医療を繙くことができる.本稿においては,中神琴渓の医療から,現代精神医学的にも意義深いと思われる具体的記述を抽出し,現代精神医学への応用の可能性を探る.
2)医療法人社団ひのき会証クリニック併設和漢診療研究所
はじめに
漢方医学は,中国の古典に端を発しつつも,室町時代後期から江戸時代を通じて現在に至るまで,わが国において独自に育まれてきた,わが国固有の伝統医学である(著者註:日本東洋医学会では,「漢方」という用語を,漢方薬を用いた湯液治療と鍼灸治療の両者を含むものと解釈している6)).近代までの漢方医学においては,精神症状の評価や精神障害に対する治療方法が掘り下げられた形跡がほとんどない.さらに,伝統的に精神療法を重んじるというコンセプトが掲げられてきているにもかかわらず,精神療法のあり方にかかわる具体的な言及はなされてきていない.そのような背景があるにもかかわらず,中神琴渓(1744~1835)(著者註:没年は1833年との説もある)は,近世から近代の漢方医学史のなかでおそらく唯一,精神障害の治療を積極的に応需し精神症状を詳述したきわめて特異な医家であり,その功績は注目に値する.本稿においては,中神琴渓の医療が伝承されている古典から,現代精神医学的視点からも意義深いと思われる具体的記述をいくつか抽出し,現代精神医学への応用の可能性を探る.
I.中神琴渓の略歴1)8)
中神琴渓は,1744年に近江国栗太郡南山田村(現在の滋賀県草津市南山田町)で出生した.通説では,農家の出身で,大津の医家中神家を継いだとされているが,同地の真宗西念寺の次男として出生したという説もある.吉益東洞(1702~1773)の晩年にその門弟となり,大津で開業後,1791年に京都堺町四条に移った.医家として晩成ではあったが,中神琴渓の医院はたいそう繁盛した.その後は,江戸に行き,諸国を遊歴した後に隠棲した.中神琴渓は,漢方医家ではあるが,梅毒の治療に水銀を用い,受刑者の死体解剖も行っており,蘭学も学んだ形跡がある.
次に,中神琴渓の医療の特徴を述べる.中神琴渓は,「臨機応変」を重んじ,卓越した病態観察眼にもとづき最適な治療戦略を提案し,個別性の高い医療を実践した.画一的な思考,固定観念,先入観を徹底的に排除し,教科書の作成をも嫌って,自身は教科書の類を一切著さなかったが,門弟たちが,師の医療が歴史に埋没することを惜しみ,後に書として編纂したため,それらの著述により中神琴渓の医療を繙くことができる.中神琴渓は,難治性の疾病や病態の相談を応需し,難病や奇病の治療に積極的にあたった.したがって,診療対象者には受診バイアスがあると想像され,患者層は当時(1800年前後)の一般的な医院の患者層とは異なっている可能性を考慮すべきだろう.時代を反映し,梅毒,肺結核,痘瘡,癩病,回虫症,条虫症などの感染症の患者が多かったようであり,精神症状が記載されている症例の多くが,器質性・症状性精神障害であった可能性もある.また,当時,加持や祈祷に頼ろうとする民意が強かったが,中神琴渓は,患者や家族らに対して,疾病としての理解と治療の必要性を説いた.治療手段としては,劇物である吐瀉剤を多用し,鍼灸,刺絡,灌法(水法)も併用した.
II.灌法(水法)
中神琴渓は,灌法(水法)すなわち冷水をかける治療法も用いていた.『生生堂傷寒約言』には,『傷寒論』の著者と考えられている張仲景の時代(約2,000年前の古代中国)に,水法が普及していたことも言及されている5).灌法は,「狂ニ限ラズ諸病ニ行フナリ」と『生生堂医譚』に記されており3),その適応が広かったことも示唆される.『生生堂医譚』には,灌法が実際に用いられた症例もいくつか提示されている.次にそのなかの1症例3)(原文は図1)を意訳して引用する.
〔意訳〕
大津土橋町木屋利助という者が,発狂して走り回り,わけのわからないことばかり言っていた.医薬を投じ,祈祷もされたが,さっぱりよくならなかった.診れば,20日も便秘していた.三黄湯に金石丸を兼用し,灌水をしたら回復した(著者註:「三黄湯」は三黄瀉心湯のことを指す.「金石丸」は中神琴渓の発案による自家製製剤で構成生薬の詳細は不明).
III.睡眠時遊行症に対して甘草瀉心湯が著効した症例
本項以下,中神琴渓の臨床が記述された古典『生生堂治験』を繙き,その内容を現代医学の視点を踏まえて掘り下げてみる.本症例は,現代の漢方医家にも大変有名な症例である.『生生堂治験』の記述4)(原文は図2)を意訳する.
〔意訳〕
近江大津の人が,娘のことで相談に来た.許嫁のいる16歳(著者註:当時の年齢表記なので「数え年」と思われる)の娘に奇病がある.毎晩,寝静まった頃に起き出して踊り始める.それがたいそう美しい舞で,毎晩曲が違っている.朝には普通に起床してくる.自覚はなく,病状を話しても,本人は不審がるばかりである.鬼か狐狸に憑かれたかのようで,これでは嫁にもやれない.祈祷もしたがよくならない.先生は,それは「孤惑の病」だとおっしゃった.往診診察をしたうえで,やはりそうだということで,甘草瀉心湯を処方なさった.数日後には,夜の舞がすっかりなくなり,嫁ぐことができて,子をなした.
「孤惑の病」とは,『金匱要略』「百合孤惑陰陽毒病脈証弁治第三」に,「孤惑の病たる,状傷寒の如く,黙々として眠らんと欲し,目閉ずるを得ず,臥起安からず.喉を蝕するを惑と為し,陰を蝕するを孤と為す.飲食を欲せず,食臭を聞くを悪み,その面目乍ち赤く,乍ち黒く,乍ち白し.上部を蝕すれば則ち声暍す.甘草瀉心湯之を主る」7)と述べられている特異な病態である.それに対する治療は,前文の通り甘草瀉心湯にほかならない.本症例のような,当時は一般に心霊現象と解され,医療の対象ではなく加持祈祷の対象とされていた病態を,中神琴渓は疾病としてとらえて漢方治療を施し治癒させていた.中神琴渓の医療は当時の民衆の一般常識を超越しており,中神琴渓が古典の記述を深く理解し確固たる医学的視点にもとづいて診療がなされていたことを本症例は物語っている.
次に,本症例に対する現代医学的解釈を述べる.毎晩,就眠後に時間が経過してから始まるエピソードで,睡眠の前半のうちにエピソードが開始されていた.朝を迎えないうちに,エピソードが自然に終息した.エピソードの内容としては,舞というまとまった動作が長い時間にわたって継続しており,情動面は安定していた.舞の曲が毎晩変わっており,てんかん発作のように同じ発作内容が反復されているわけではなかった.本人にはまったく自覚がなかった.したがって,本症例は睡眠覚醒移行障害と考えられ,病状の特徴からノンレム睡眠関連睡眠時随伴症の一種である睡眠時遊行症と診断される.治療においては,漢方医学的診断である「証」に随って投与された甘草瀉心湯が著効した.
本症例のように,精神症状が詳細に聴取され記述されている漢方古文献は,中神琴渓の治験のほかに例がない.本症例を参考として,甘草瀉心湯が現代の実臨床にも応用されている2).ただし,元山は,本症例の引用にあたり,舞が始まる時刻を「毎夜のこと辰巳の時刻になって」と記述している2)が,「辰巳の時刻」は午前8~10時頃を指すため,論旨に破綻を生じており,解釈上の誤りと思われる.なお,「孤惑の病」は,その定義が明確ではないため,睡眠時随伴症以外の疾患を含む幅広い症候群と考えられる.
IV.「癲癇」の症例
『生生堂治験』の症例の記述4)(原文は図3)を意訳する.
〔意訳〕
一女性.幼少の頃から癲癇を患い,立つと意識を失って倒れ,しばらくすると回復するという発作が,かれこれ30年余りにわたり,毎日1~2回はあった.あちこちの医者から治療を受けたが,奏効しなかった.先生が往診したところ,脈は緊数,腹には心下硬満,乳下悸動(著者註:「乳下悸動」は腹部動悸の一種とみなす)がみられた.
本人が,ぼうっとして,よく眠れず,食も進まない状態がずっと続いている,と述べた.愁いを帯びた顔つきで,とても憐れにみえたため,先生が慰めて,治療できる,とおっしゃり,柴胡加竜骨牡蛎湯を投じたところ,先生の言葉を信じて内服し,すこぶる元気になった.
さらに,瓜蔕散を服用させたところ,臭い粘稠痰を多量に吐いた.しばらくは,5~6日に1回ぐらい発作が現れていたが,16回吐剤を用いたところ,1年ですっかり治癒した.それまでは,雷鳴を聞けば発作を起こしていたが,雷鳴が轟いても平気になった.患者は先生への恩を一生忘れなかった.
本症例が本当にてんかんだったのか,精神医学的診断は情報不足のため不明である.現代医学的には,失神のようにも読める.発作は,雷の閃光により誘発されていたのではなく,雷鳴によって誘発されていたようである.漢方医学的証に随って投与された柴胡加竜骨牡蛎湯が抑うつ症状に著効した.さらに,吐剤である瓜蔕散で解毒し,根治を図った.もっとも,瓜蔕散は,原料生薬の確保が困難となり,また吐かせる治療の危険性も高いことから,現在は使用されなくなっている.その他,本症例からは患者-医師関係の重要性も示唆される.
V.解離性発作を思わせる症例
『生生堂治験』の症例の記述4)(原文は図4)を意訳する.
〔意訳〕
50歳代の女性.怒ったときに,少腹すなわち下腹部に物があるような感じで,それに心を衝き上げられ,意識を失って倒れ,歯をくいしばって開口できず,1時間ほどで自然に回復するというエピソードが,月に1~2回あった.先生が往診して診察したところ,胸腹に動悸がみられた.柴胡加竜骨牡蛎湯を投与し,数十日したら治癒した.
解離性発作を思わせる50歳代女性の症例である.脚気衝心あるいは奔豚と類似するような気の上衝があって,意識消失をきたしていた.意識消失している1時間ぐらいの最中には,食いしばりがあった.腹動がみられたことから,漢方医学的証に随って柴胡加竜骨牡蛎湯が処方されたところ,数十日の経過で治癒に至った.
VI.誤治のために熱性せん妄を生じたと思われる症例
『生生堂治験』の症例の記述4)(原文は図4)を意訳する.
〔意訳〕
一男性.太陽と陽明の合病による下痢を患っていた(著者註:「太陽と陽明の合病」とは,熱が体の深部にこもっているにもかかわらず,発汗することができなくなっていて,行き場のなくなった水が消化管の管腔にあふれ,下痢が止まらなくなっている病態のことを言う).発汗させる処方(著者註:おそらく,太陽と陽明の合病に通常適用される葛根湯を意図しているのではないかと思われる)を受けたところ,汗が止まなくなった.7~8日経ち,四肢が少し冷えているのに,日中はかえって赤くなっていた.自分を責めるようなことを言い,天を言い,神を言い,恍惚として,自分の思っていることを言っているわけではなさそうだった.往診した医者が,「心虚」と弁証して真武湯を投与したが,その夜,耳が聞こえなくなり,舌がこわばって,病勢が一層強くなった.
先生が改めて往診したところ,脈は沈遅,舌は黒苔を被り,腹には燥屎が溜まっていた.大承気湯を投じたところ,1服が終わらないうちに,かえって下痢が止まり,空をつかみ,うわ言を言い,手足が焼けるように火照った.さらに大承気湯を3服飲ませたが,亥の刻(著者註:午後10時頃)から卯の刻(著者註:午前6時頃)まで同じ状態だった.さらに生蓮根汁を飲ませ,大承気湯を十数服させたところ,乾燥便と黒色粘液を排泄し,多量に発汗して,落ち着いて眠りに就いた.その後十数日で軽快したが,心下煩満し,食欲不振があったため,小柴胡湯を30日余り飲ませたところ回復した.
誤治のために,全身に熱がこもってしまう病態,すなわち「陽明病」に陥ったとみられる症例である.精神症状は,熱性せん妄が疑われるものである.大承気湯を投与したところ,好転反応と考えられる奇異反応である「瞑眩」が現れた.大承気湯を十分に投与して瀉下した結果,多量に発汗した後,落ち着きが得られた.残遺症状を小柴胡湯で治療した(このような後始末の追加治療のことを漢方医学では「調理」と言う).なお,上述のように「熱邪」を重視して,熱性せん妄ではないかと解釈したが,現代精神医学的診断をしっかり確定できるほどの情報が十分に記載されているわけではなく,統合失調症圏の急性精神病の経過であった可能性もあり,現代精神医学的診断の確定は困難である.
VII.感染症を契機としてせん妄をきたした症例
『生生堂治験』の症例の記述4)(原文は図5)を意訳する.
〔意訳〕
30歳を過ぎた男性.冤罪で長らく投獄されていたが,恩赦があって解放された.痩せこけて着る物にも困るほどで,閉居して人に会わないようにしていた.ある日,傷寒に罹患し,悪寒戦慄があって四肢末端には少し冷えが現れ,対話するような独語がみられた.先生が往診したところ,小腹急結がみられ頻尿があったため,「熱結膀胱」だとおっしゃって,桃核承気湯を6服処方した.その晩,大量に鼻出血があり,さらに数合の下血もみられた.そうしたら,すっかり回復して憤りもなくなっていた.
「傷寒」すなわち感染症に罹り,感冒初期の病態である「太陽病」を経て,治癒せずにこじらせてしまい,「下焦」すなわち下腹部に熱がこもってしまう「熱結膀胱」の病態に至った.それに伴い,せん妄を思わせる病態となった.「小腹急結」すなわち左下腹部の攣急がみられたことから,桃核承気湯の証と考えられ,随証投与された桃核承気湯により治癒した.せん妄のみならず,感染症に罹患する前からあった内的不穏や焦燥も消退するに至った.本症例では,「傷寒」の経過のなかで対話性幻聴などの精神病症状が出現していたように記述されていることから,感染症の経過とみてせん妄と暫定診断したが,感染症罹患を契機として精神病症状が顕在化した統合失調症圏の障害であった可能性も否定できない.また,「傷寒」に罹患する以前の引きこもり状態については詳細不明のため,特定は困難ながら,神経衰弱状態を呈する基礎疾患,あるいは統合失調症の前駆状態が,せん妄とは別個に存在していた可能性も考慮しておかなければならないだろう.
VIII.急性錯乱状態を呈した旅人の症例
『生生堂治験』の症例の記述4)(原文は図6)を意訳する.
〔意訳〕
堺町蛸薬師の南,近江屋清兵衛が人を使わし,旅の客が急病になったと往診を要請してきた.先生が往診してみると,40歳ばかりの人で,呼吸が促迫し,咽からか細い声が聞こえた.四肢末端が冷たくなり,眼は動かず,まるで旗が風で揺らいでいるかのようにうつろだった.発病時には,室内を走り回り,誰もいないのに叱りつけたり,狂って怒鳴ったりしていて,抑えようとすれば噛みついてきたため,どうにもならなかった.先生は曲池(著者註:曲池LI 11は肘窩の経穴)を刀で破ったが出血しなかった.膏肓(著者註:膏肓BL 43は背部の経穴)を刺してもほんの少ししか出血がなかった.口唇を刺すと黒い血があふれ,ようやくおとなしくなった.脈を診ると何とも言えない散乱した脈だった.先生は,痧病(著者註:「痧病」は,コレラを指すこともあるが,ここではコレラではなく,陳旧性の瘀血を指すものと思われる)の急性増悪だとおっしゃり,桃核承気湯を3服処方した.何日か経ち,患者は無事旅立ったとの知らせが届いた.
急性一過性精神病性障害を思わせる旅人のエピソードで,患者は急性錯乱状態であった.刺絡による処置も行われた.激しい興奮のため,おそらく腹診ができなかったのではないかと思われ,病態から推測して証を立てて投与された桃核承気湯が奏効した.
おわりに
中神琴渓の臨床が生々しく記録された古文献を繙き,現代精神医学的観点からの解釈を加えた.中神琴渓の医療の実際や臨床現場での医療行動から,現代精神医療にも通じる次のようなポイントが示唆された.
1.精神症状の具体的な把握と記録の重要性
中神琴渓が,一般的な漢方医学的所見(脈候,舌候,腹候など)のみならず,精神症状についても詳細に診ていたことによって,具体的な症例記録が上述のように世紀を超えて現代に伝わっている.現代医学的視点から解釈するには,とりわけ診断面において限界があるものの,現代人の目から見ても,大変興味深く,有意義な臨床経験が記述されているため,中神琴渓の医療に大いに学ぶべきものがあることがここに改めて認識された.また,詳細な臨床記録を後世に残すことの大切さも改めて認識された.
2.型にとらわれすぎない個別性を重視した医療の実践
VIIの症例は内的不穏が強いものの精神運動興奮状態は呈していなかったようであり,VIIIの症例は急性錯乱状態を呈し,激しい精神運動興奮のために診察することさえも難しい病状であった.この2症例は病像が大きく異なっているが,同じ桃核承気湯によって治療がなされた.しかも,VIIIの症例は本来であれば治療方剤の決定にあたって欠かすことのできない腹診が実施できないまま,痧血病態が原因と見抜いて桃核承気湯が選択された.一方,VIIIの症例ほど激しくはないとしても,同様に落ち着かない状態となっていて,VIIIの症例の病態との類似点が多いVIの症例においては,桃核承気湯ではなく大承気湯が選択された.さらに,IIの症例では灌法,IVの症例では吐剤,VIIIの症例では刺絡もしくは瀉血が併用された.そのような補完的治療方法の使い分けは,見かけの病状だけではなく,その病態を生じた機序をも瞬時にして読み取ることができなければ,適材適所に運用していくことは困難である.このように,中神琴渓が単に「証」という型に落とし込んで流れ作業的に投薬していたのではなく,個々の症例における病態の成り立ちについて,その都度じっくりと洞察しながら,最善の治療プランを状況に応じてこまめに組み立てていたことがうかがわれる.
3.鋭い病態観察眼を養うことの重要性
VIの症例のような不穏状態を呈する患者を目の前にして,大承気湯という劇薬を投与した後,「瞑眩」と思しき反応が現れ,荒れた病状によって修羅場となっていたなかで,その場で観察しながら,効果が現れるまで冷静に大承気湯を根気よく投与し続けるということは,現代の熟練した漢方医家でも至難の業である.投与した薬がすぐには報われないなかで,これだけ確信をもって治療をやり遂げるには相当なスキルが必要であり,とりわけ病態観察が的確になされていなければ,治療途中で迷いを生じて諦めてしまうだろう.中神琴渓の病態観察眼が並外れて鋭かったと想像され,とりわけ本症例の治療経過からは,そのような観察眼を養うための研鑚を積むことの重要性が示唆される.
4.正確な病態理解にもとづく治療戦略の立案
IIIの症例で述べたとおり,中神琴渓は,古典の記述を盲目的に暗記するのではなく,古典に記載された漢方医学的証を決定づける症候やその成り立ちについて,経験に裏打ちされた実践的な病態理解をしっかりと身につけており,その病態に相応しい治療戦略の提案が,説得力をもって個別的になされていたことがうかがわれる.
5.治療にかかわるインフォームド・コンセントの重要性
特にIIIの症例においては,動物霊の憑依が原因ではなく,疾病として生じたものであり,それゆえに加持祈祷は報われないが薬物療法が可能であると説明されたことによって,漢方薬がきちんと服用されたと考えられ,著効して数日のうちに症状が消退した.このように,文脈から,インフォームド・コンセントにより治療同意が得られ,治療が円滑に進んだことが示唆される.
これらの5項目は,時代を超えて現代の精神科医としても求められるべき基本的スキルに相違ない.加えて,漢方医学的には,瀉剤などの劇物をためらわず確信をもって投与できることの重要性も特筆に値する.呉秀三は吉益東洞の著作を編纂し,そこから多くの学びを得ているが,吉益東洞の門弟である中神琴渓からも改めて学ぶべきものがあるだろう.とりわけ,現代医療においても用いられている漢方基本方剤(柴胡加竜骨牡蛎湯,大承気湯,桃核承気湯など)を,漢方医学的証に随って適材適所に使いこなすことによって,向精神薬がなかった時代に劇的な効果が発揮されていたことには,漢方専門医としても精神科専門医としても驚嘆を禁じえない.
編注:本特集は,第117回日本精神神経学会学術総会シンポジウムをもとに山田和男(東北医科薬科大学病院)を代表として企画された.
なお,本論文に関連して開示すべき利益相反はない.
1) 松田邦夫: 江戸期における先達の医訓. 日本東洋医学雑誌, 44 (3); 275-280, 1994
2) 元山幹雄: 甘草瀉心湯が奏効した睡眠時遊行症(夢遊病)の一症例. 日本東洋医学雑誌, 46 (5); 761-764, 1996
3) 中神琴渓: 生生堂医譚. 1796〔新日本古典籍総合データベース 京都大学附属図書館富士川文庫. (https://kotenseki.nijl.ac.jp/biblio/100314693/viewer) 〕(参照2021-11-13)
4) 中神琴渓: 生生堂治験. 1804〔新日本古典籍総合データベース 京都大学附属図書館富士川文庫. (https://kotenseki.nijl.ac.jp/biblio/100316055/viewer) 〕(参照2021-11-13)
5) 中神琴渓: 生生堂傷寒約言. 1820〔新日本古典籍総合データベース 京都大学附属図書館富士川文庫. (https://kotenseki.nijl.ac.jp/biblio/100314695/viewer) 〕(参照2021-11-13)
6) 日本東洋医学会: 漢方の診察 2-5 治療の特徴 鍼灸. (http://www.jsom.or.jp/universally/examination/sinkyuu.html) (参照2021-11-13)
7) 大塚敬節主講, 財団法人日本漢方医学研究所編: 金匱要略講話 創元社, 大阪, p.83-84, 1979
8) 山田光胤: 中神琴渓・小伝並びに解題. 中神琴渓(大塚敬節, 矢数道明責任編集, 近世漢方医学書集成17). 名著出版, 東京, p.5-52, 1979